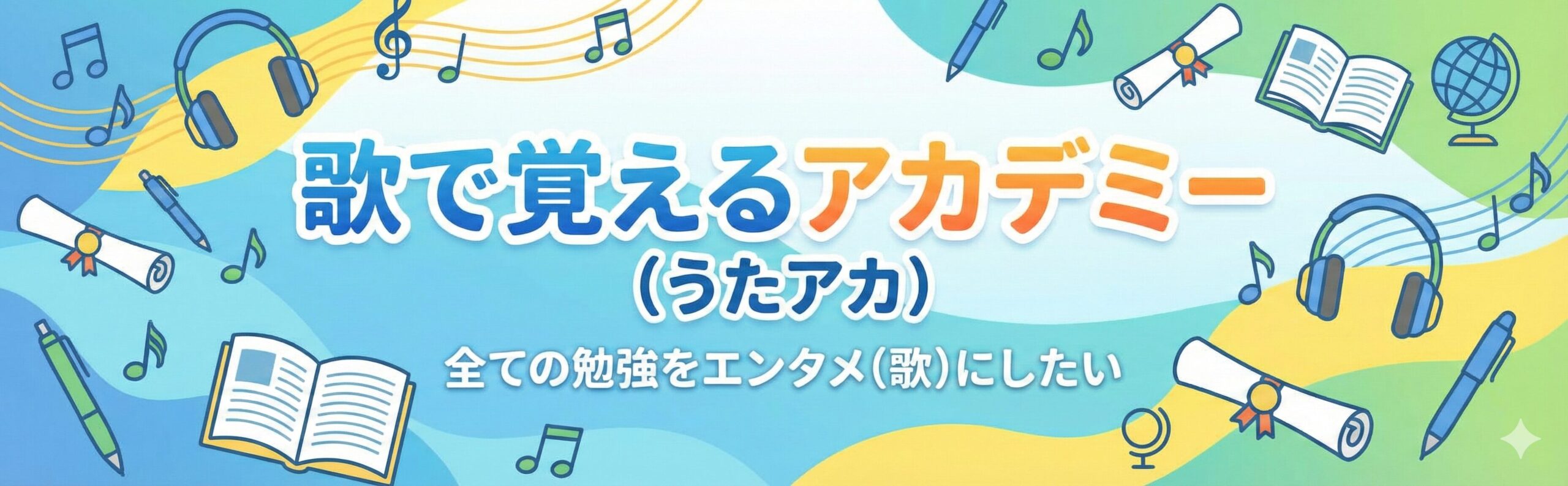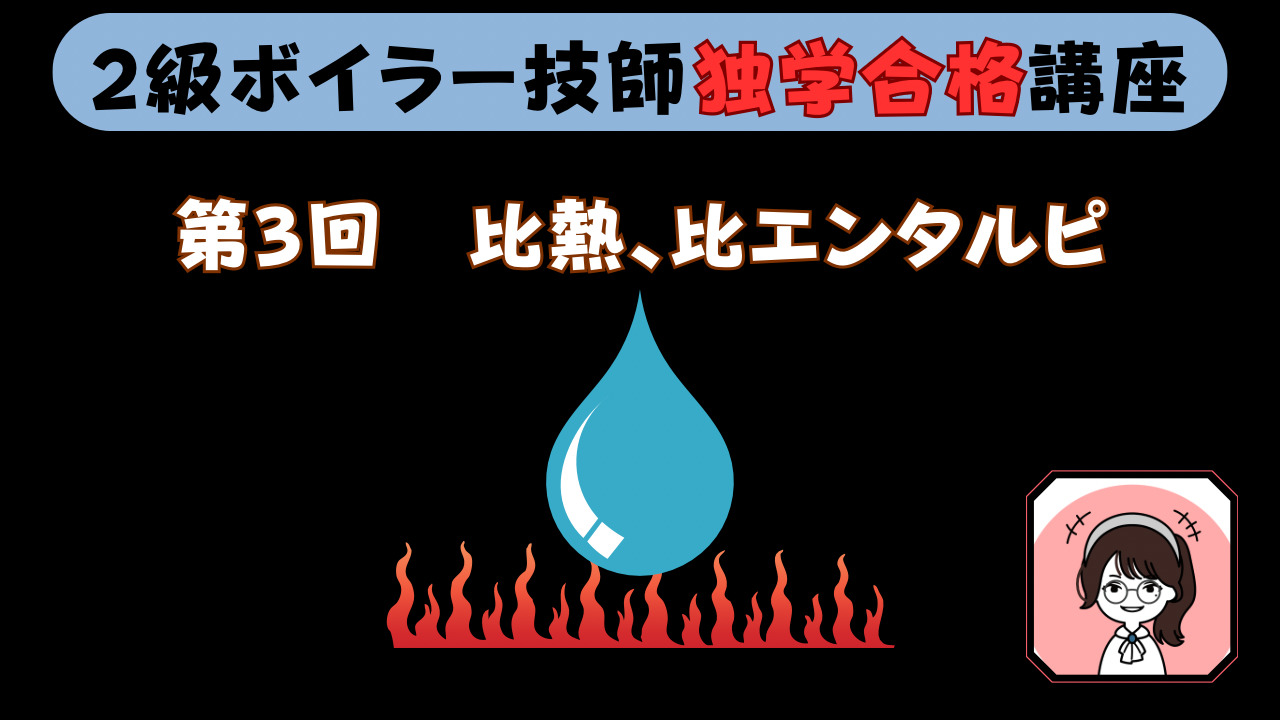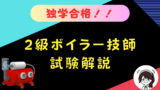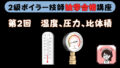こんにちは、資格マニアのパル子です。今回は、2級ボイラー技士免許試験に出題される「比熱と比エンタルピ」について解説します。
過去問を分析して、特に出題頻度が高いところは太字にしておりますので、重点的に覚えましょう。

現在は会社員として働きながら、通勤時間や休日に一人でコツコツ動画を作っています。まだ更新頻度は高くありませんが、この『うたアカ』を、日本一楽しく学べるサイトにすることが夢です。皆さんからの『チャンネル登録』や『いいね』が一番の原動力になり、次の動画を作るスピードが上がります! ぜひ応援よろしくお願いします。
コンテンツ
熱量と比熱
熱いものと冷たいものを接触させると、熱いものは温度が下がり、冷たいものは温度が上がります。これは熱が熱いものから冷たいものに伝わるからですが、この熱の量を表すものを、熱量と言い、その単位をジュール[J]と言います。
ある物体1kgを1℃上げるのに必要な熱量を比熱といい、単位をkJ/kg・Kと表します。 同じ量の熱を加えても物体によって上がる温度は異なります。
例えば、水の比熱、つまり水1kgを1℃だけ上げるために必要な熱量は4.187kJですが、銅1kgを1℃だけ上げるために必要な熱量は0.379kJであり、加えた熱量が同じであれば、銅の方が10倍以上も多く温度が上がることになります。
気体の比熱の場合、液体や固体の比熱とは違い、次の二つの表し方があるので,注意する必要があります。
一つ目は、圧カ一定で温度1K(1℃)を上げる場合で、定圧比熱といいます。二つ目は、体積一定で温度1K(1℃)上げる場合を定容比熱(定積比熱)といいます。
顕熱、潜熱、比エンタルピ
顕熱と潜熱
物体に熱を加え温度が上昇するように、温度計により目で見て分かる熱量のことを顕熱といいます。
一方で、水が水蒸気になるように、物体の状態が変わる時に加えた熱は、その状態変化に使われて実際の温度に変化を与えません。このような熱を潜熱といいます。
また、潜熱の中でも液体の蒸発に使われる熱を蒸発熱といい、標準大気圧における水の蒸発熱は、水の質量1kgについて2257kJとなっています。
比エンタルピについて
ある物質1kgの顕熱と潜熱を合計した全熱量を比エンタルピ[kJ/kg」といいます。
例えば、20℃の水の比エンタルピは、水1kgを20℃上げる顕熱である20×4.187=83.74[kJ/kg]となります。
また、100℃の飽和水蒸気の比エンタルピは水1kgを100℃上げる顕熱に、蒸発熱を加えた、100×4.187+2257=2675.7[kJ/kg]となります。
見ていただきありがとうございました。
次回の解説
今回の説明に関する過去問はこちら
【問題】標準大気圧の下で、質量1kgの水の温度を1K(1℃)だけ高めるために必要な熱量は約2257kJである。
【解答】誤り。問題の値は4.2kJであり、2257kJは水の蒸発熱の値である。
【問題】質量1kgのある物体の温度を1K(1℃)だけ高めるために必要な熱量を、その物体の潜熱という。
【解答】誤り。潜熱ではなく比熱である。
【問題】水の温度は、沸騰を開始してから全部の水が蒸気になるまで一定である。
【解答】正しい。
【問題】飽和水の比エンタルピは、飽和水1kgの顕熱である。
【解答】正しい。
【問題】飽和蒸気の比エンタルピは、飽和水1kgの気化熱である。
【解答】誤り。飽和蒸気の比エンタルピは、飽和水1kgの比エンタルピに蒸発熱を加えた値である。
このページを動画で見たい方
2級ボイラー技士免許試験の解説一覧はこちら
本気で試験に受かりたい方への1冊
試験突破の最も効率的な方法は過去問を解きまくることです。特に問題数が多く解説も丁寧な以下の過去問集をおすすめします。